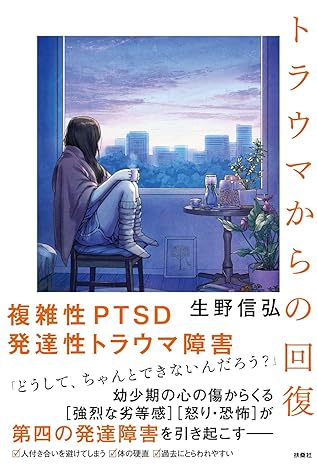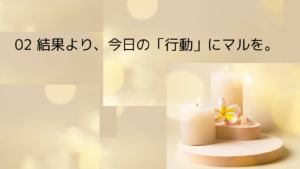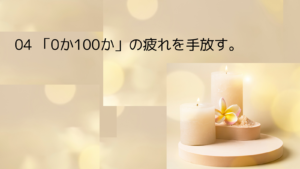はじめに:「またやってしまった…」と責めてしまうあなたへ
食べることに苦しんでいませんか? 「また過食してしまった」「ちゃんと食べたいのに食べられない」と、つらくなることはありませんか。
実は、こうした症状には脳内の神経伝達物質やホルモンの働きが大きく関わっていることがあります。 摂食障害は「気持ちの問題」だけでなく、生活リズムや栄養状態の乱れが脳と体に影響し、食行動をコントロールしにくくしているのです。
今回は、摂食障害の回復に欠かせない「神経伝達物質」「ホルモン」「生活習慣」のつながりについて、やさしく解説していきます。
生野 信弘
1988年長崎大学医学部卒業。医学博士。
2001年に内科から精神科に転向後は、過食症の対人関係療法とともに、「複雑性PTSD」などトラウマ疾患を専門に外来診療を行ってきた。『トラウマからの回復』の著者でもある。
摂食障害と脳・ホルモンの関係とは?
摂食障害の背景には、「自分の意志ではどうにもならない」ような感覚がある方も多いと思います。 実際に、脳や体の働きに関係する神経伝達物質やホルモンが、気分や食欲、行動に大きく影響していることがわかっています。
ここからは、「神経伝達物質」「生活リズム」「ホルモン」それぞれの働きと影響を、わかりやすく整理して見ていきましょう。
神経伝達物質が心と食欲に与える影響
セロトニン・ドーパミンの役割と感情の波
セロトニンは心の安定に関わる物質で、不足すると「落ち着けない」「イライラする」「甘いものがやめられない」といった症状が出やすくなります。 一方、ドーパミンは「快」の感覚ややる気・集中力に影響し、働きが弱まると「何をしても楽しく感じられない」「何かで刺激を得たい」という衝動的な食行動につながることがあります。
これらの神経伝達物質は、規則正しい生活や十分な栄養によって整いやすくなりますが、過度な食事制限や夜更かしが続くと、脳に必要な栄養素の不足や体内時計の乱れによって分泌リズムが崩れやすくなります。
その結果、気分の不安定や食欲のコントロールが難しくなり、摂食障害の悪化につながることもあるのです。
ノルアドレナリンとストレス反応
ノルアドレナリンは、「集中力を高める」「ストレスに備える」ために必要な神経伝達物質です。 過剰に分泌されると不安や緊張を高め、逆に不足すると無気力感や注意力散漫になりやすくなります。
バランスを保つには、十分な睡眠や栄養がとても重要です。
このように、脳内の神経伝達物質の働きは、心の状態や食行動と密接に結びついています。
生活リズムと栄養の乱れがもたらす影響
睡眠不足が「過食スイッチ」を押す
夜更かしや眠れない日が続くと、脳内のセロトニンが不足しやすくなります。その結果、不安やストレスを抑える手段として「食べること」に頼りやすくなります。
また、睡眠不足は食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌を増やし、一方で満腹感を感じさせる「レプチン」の働きを弱めるため、満腹感が得にくくなり過食傾向に拍車がかかります。
さらに、グレリンは睡眠の質を低下させる働きもあるため、睡眠不足と過食の悪循環に陥りやすくなります。
「過食スイッチ」が入る、睡眠不足以外のきっかけとその止め方についてはこちらを参考にしてください。

栄養不足が“脳の材料不足”に
神経伝達物質やホルモンの生成には、たんぱく質、鉄、ビタミンB群、亜鉛などの栄養素が不可欠です。極端な制限食や偏食によってこれらが不足すると、脳の働きが鈍り、感情を感じにくくなったり感情のコントロールが難しくなったりします。
食と生活の乱れが心にどう影響する?──実際のケースから見えること
たとえば、夜中に過食を繰り返していたAさん(仮名)は、朝が来ると自己嫌悪に陥り、「もうやめよう」と決意するものの、また夜になると気持ちが不安定になり、同じことを繰り返していました。
カウンセリングで詳しく聞くと、睡眠が浅く、ほとんど朝日を浴びていないことがわかりました。そこで、まずは「毎朝同じ時間に起きて光を浴びる」ことから始めたところ、1週間ほどで気持ちの浮き沈みが少しずつ落ち着き、過食の頻度も減っていきました。
このように、生活の乱れが神経伝達物質の働きに影響し、結果として食行動に表れることがあるのです。
食事制限と脳のバランスの崩れ
過度な食事制限が続くと、脳内の神経伝達物質をつくる材料(アミノ酸やビタミンなど)が不足し、セロトニンやドーパミンの分泌も乱れやすくなります。
このような状態では、気分が落ち込んだり、衝動的な過食が起こりやすくなります。無理な制限の結果として食行動が乱れ、さらに自己否定が強まる…という悪循環が生まれやすくなるのです。
食欲・ストレス・睡眠をつかさどるホルモンの連鎖
グレリン・レプチン・オレキシンの関係
食欲や覚醒に関わるホルモンは、バランスよく働くことで、私たちの体と心のリズムを保っています。ここでは、摂食障害に関係する代表的なホルモンの働きと、乱れたときの影響について見ていきましょう。
- グレリン:空腹を感じさせるホルモン
- レプチン:満腹を知らせるホルモン
- オレキシン:覚醒や摂食行動を促すホルモン
これらのホルモンは、規則正しい生活や栄養バランス、良質な睡眠によって整えられていますが、生活リズムが乱れるとそのバランスも崩れやすくなります。
睡眠不足が続くとグレリンが増えて空腹感が強まり、レプチンの働きが弱まって満腹感を感じにくくなります。また、グレリンの増加は「オレキシン」というホルモンの分泌も刺激し、さらに眠れなくなるという悪循環を生み出します。
このようなグレリンとオレキシンの相互作用によって、「眠れない → 食欲が増す → さらに眠れない」という負のループに陥ると、過食や気分の不安定さが強まり、摂食障害の悪化につながることがあります。
コルチゾールとメラトニンが乱れるとどうなるか
- コルチゾール:ストレスを感じたときに分泌され、血糖値を上げてエネルギーを確保しようとします。ただし、これが慢性的に続くと血糖調節が乱れ、「血糖値スパイク(急上昇・急降下)」が起こりやすくなります。結果として、甘いものを無性に欲したり、イライラや不安感が強まり、感情のコントロールが難しくなることがあります。
- メラトニン:コルチゾールが「体を目覚めさせるホルモン」であるのに対し、夜に分泌が増える「メラトニン」は「セロトニン」から作られる「眠りを促すホルモン」です。朝に増えるコルチゾールとはシーソーのような関係です。
この2つは体内時計のリズムを保つうえで連携しており、朝はコルチゾールが増え、夜にはメラトニンが増えるというサイクルが理想です。
生活リズムが乱れたり、ストレスや夜更かしが続くことでこのバランスが崩れると、睡眠の質が低下し、さらに食欲や感情のコントロールが難しくなっていきます。
このように、ホルモンの連携が崩れると、心身のバランスが不安定になり、食欲や感情のコントロールがより難しくなるのです。
自分のリズムを取り戻すために、できること
まずは「ちょっと整える」から
摂食障害の回復は、「食べ方」だけを変えることではありません。
心と体を整えるためには、生活リズムや環境を少しずつ見直すことも大切です。
「ちゃんとやらなきゃ」と思うほど、ハードルが高くなってしまうこともあります。だからこそ、最初の一歩は「できることを少しだけ」で大丈夫です。
たとえば…
- 朝起きたらカーテンを開けて光を浴びる
- 水を一杯飲む
- 5分だけ外を歩いてみる
- 眠る前のスマホ時間を10分減らす
ほんの小さなことでも、脳やホルモンのリズムを取り戻すきっかけになります。
「整えること」が、心の支えになる
生活リズムが整いはじめると、気分の波や衝動も少しずつ落ち着いてきます。
それは、あなたの体の中で、神経伝達物質やホルモンのバランスが整ってきたサインかもしれません。
「どうせ変われない」と思ってしまう日もあるかもしれません。
でも、あなたが一歩ずつ整えていくことで、回復の土台は少しずつ築かれていきます。
一人で難しいときは、支えてくれる人や場所を頼ってもいいのです。
あなたには、整えていく力がちゃんと備わっているのです。
栄養と心のケアはセットで考える
心のストレスがホルモンバランスを乱す
日常的なストレス、過去のつらい経験、人間関係の摩擦などは、知らず知らずのうちにホルモンバランスに影響を与えます。ストレスが強いと、初期にはコルチゾールが過剰に分泌されますが徐々に低下し、過食や無気力の原因になることもあります。
「栄養だけでは解決しない」心の背景も大切に
たとえ栄養や生活リズムが整っていても、心の中に「満たされないもの」があると、摂食障害の症状は繰り返されることがあります。カウンセリングでは、そうした背景にも寄り添いながら、一緒に整えるお手伝いをします。
ゆっくりでも大丈夫。あなたのペースで回復していこう
摂食障害の症状には、脳やホルモン、生活のリズムが深く関わっています。 「止めたくても止められない」と感じるのは、あなたの意志の問題ではなく、心と体のしくみが追いついていないだけかもしれません。
生活リズムを少しずつ整えていくことは、あなたの中に眠る「回復する力」を引き出す第一歩になります。
できることから、少しずつ。 焦らなくても大丈夫。
もし一人では難しいと感じたら、専門家と一緒に取り組むことも、あなたを支える大切な選択肢です。
あなたの回復は、きっとあなたらしい形で進んでいきます。
心と体の声に耳を傾けながら、やさしく整えていきましょう。
回復された方・変化を実感された方
実際の体験談を読む
体験カウンセリング
(オンライン)

上畠 真紀
公認心理師、精神保健福祉士
経験
18年以上のカウンセリング経験(精神科・心療内科)
専門分野
摂食障害、気分障害、トラウマ、対人関係