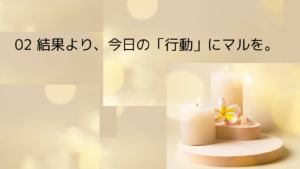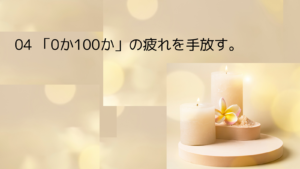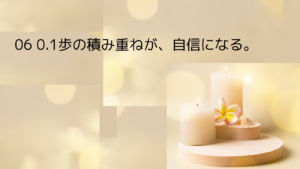気づいたら食べすぎてしまったり、食べるのが怖くなったり。
そんな自分を責めてしまう日々が続いていませんか?
食べること、食べないことに、自分でも説明できないような不安や焦りがついてまわる。
その背景には、「人とのつながり」にまつわる深い痛みが隠れていることがあります。
この記事では、摂食障害と「愛着(人とのつながり方)」の関係について、 心のしくみをやさしくひもときながら解説していきます。 食べ方の裏にあるあなたの気持ちを、少しずつ理解していくきっかけになれば幸いです。

上畠 真紀
公認心理師、精神保健福祉士
経験
18年以上のカウンセリング経験(精神科・心療内科)
専門分野
摂食障害、気分障害、トラウマ、対人関係
愛着とは?──人とのつながり方の“土台”
幼少期に育まれる、心の安心感のベース
「愛着」とは、簡単に言えば“人とのつながり方の土台”。 特に幼いころに、親や身近な大人との関係の中で築かれます。
たとえば、不安なときや怖いときに、誰かがそばにいて安心できた経験。 夜泣きしたときに抱っこしてくれた、熱を出したときに一緒にいてくれた―― そうした体験が、「困っても誰かを頼っていい」「助けてもらえる」という感覚を育てます。
一方で、泣いても放っておかれた、怖いときに見て見ぬふりをされた、 気持ちを否定された――そんな体験を重ねると、 「感じるのは危ない」「誰にも頼れない」と感じるようになるかもしれません。
安心できない関係が、感情や人との距離感に影響する
反対に、安心できる関係が築けなかったり、気持ちを受け止めてもらえなかったりすると、 「頼ったら迷惑かも」「感じるのは危ない」と思うようになってしまうことがあります。
その結果、人との距離をうまく取れなかったり、過剰に合わせすぎてしまったり、 反対に誰にも近づけずに孤立してしまったりすることもあります。
愛着は「食べ方」にも影響してくる
このように、愛着のあり方は、その後の人間関係や感情の扱い方に深く影響します。
そしてそれは、私たちの「食べ方」にも、知らず知らずのうちに反映されるのです。
「愛着」とは、簡単に言えば“人とのつながり方の土台”。
特に幼いころに、親や身近な大人との関係の中で築かれます。
たとえば、不安なときや怖いときに、誰かがそばにいて安心できた経験。
そうした体験が、「困っても誰かを頼っていい」「助けてもらえる」という感覚を育てます。
感情の調整と愛着の関係
感情の調整とは、感じた気持ちを必要以上に抑えすぎたり、逆に爆発させたりすることなく、自分の内側でうまく扱えるようにする心の働きです。
心理学では「情動制御(エモーション・レギュレーション)」と呼ばれ、発達心理学の観点からも、幼少期にどのように周囲の大人と関わったかがその力の土台になると言われています。
感情調整の力をわかりやすく説明すると、「心の中の温度計」のようなものです。
熱くなりすぎたら冷ます方法を知っていて、冷えすぎたら温めることもできる。
そんな温度調整機能を、子どもは周囲との関わりの中で少しずつ身につけていくのです。
感情を受け止めてもらえる体験が土台になる
人は誰でも、怒ったり悲しくなったり、不安になったりします。
その強い感情をどう扱うかは、子どもの頃の人間関係の中で自然と学んでいきます。
たとえば、泣いているときに「怖かったんだね」と大人が受け止めてくれると、 「感じてもいいんだ」と安心でき、感情を調整する力が育っていきます。
感情を抑えるために、「食」が使われることもある
逆に、感情を否定されたり無視されたりすると、 「感じてはいけない」「感じたくない」と、感情を抑えるクセがつくことがあります。
その結果、自分の気持ちを処理できなくなり、 代わりに「食べる/食べない」という行動で感情をコントロールしようとすることがあるのです。
こうして、食べ方の問題は、実は「感情を感じられない」「表現できない」ことのサインである場合も多いのです。
過食・拒食に込められた、心のメッセージ
過食に隠れている「満たされなさ」と不安
過食には、「さみしい」「満たされたい」「誰かに寄り添ってほしい」といった、不安や孤独を埋めようとする心の動きが隠れていることがあります。
その行動の奥には、「誰かにわかってほしい」「自分の苦しさに気づいてほしい」という切実な気持ちがあることも少なくありません。
たとえば、Aさん(仮名・30代女性)は、仕事のプレッシャーや人間関係のストレスで心がいっぱいになると、帰宅後、無意識に食べ物に手が伸びてしまうそうです。
「お菓子を食べている間だけはホッとする」「何も考えなくてすむ」と話してくれました。
ただ、食べ終えたあとには決まって後悔や罪悪感が押し寄せてきて、「またやってしまった」と自分を責め、涙が止まらなくなることもあるといいます。
Aさんは、「過食は悪いことだ」と感じつつも、それがやめられないことでさらに自己否定を強めてしまう悪循環に陥っていました。
話を重ねるうちに、過食の前には「誰にもわかってもらえない」「ひとりで抱えてつらい」といった孤独感や無力感が強まっていることに気づいていきました。
実は、Aさんは子どもの頃から「がんばり屋さん」と言われることが多く、弱音を吐いたり、助けを求めたりすることが苦手でした。
どんなにしんどくても「大丈夫」とふるまうクセがついていたそうです。
けれど、大人になっても「がんばらなければ愛されない」という思いが根強く残り、無理を重ねてしまう。そんなとき、過食は「心が限界を訴えるサイン」として現れていたのかもしれません。
過食という行動は、心の苦しさを一時的に和らげるための自己防衛の手段でもあります。
その奥にある「気づいてほしい」「安心したい」という思いを見つめることが、とても大切なのです。
拒食に込められた「コントロール」と自己防衛
Bさん(仮名・20代女性)は、幼いころからまわりの反応に敏感で、「どうすれば喜ばれるか」を常に考えて行動してきました。
表向きは明るくしっかりした印象を持たれやすい一方で、自分の本音を出すことにはためらいがあり、「がっかりさせたくない」という気持ちが強くあったといいます。
子どもの頃、何気ない一言を気にして落ち込むことがよくあり、自分の言動が人にどう影響するかに敏感だったそうです。
気づけば、まわりの期待に応えることで自分の存在価値を感じようとしていたのかもしれません。
思春期には、「完璧でいたい」「期待を裏切りたくない」という思いが強まり、次第に食事を減らすようになりました。
彼女にとって、食をコントロールすることは、外からの期待や評価に揺さぶられ続ける日々の中で、唯一自分自身を守れる手段だったのです。
その背景には、安心して甘えたり、弱さを見せたりする経験がうまく育たなかった愛着の傷があることも考えられます。
「ありのままの自分でいても、受け入れてもらえる」 という感覚が十分に育っていなかったとすれば、食のコントロールを通じて「理想の自分」を保とうとするのは、自然なこころの動きなのかもしれません。
食べ方の背景には、つながりの痛みがある
このように、拒食も過食もただの問題行動ではなく、 心が自分を守ろうとしてきた“対処のかたち”なのです。
それぞれの食行動の背景には、「つながりたいのに、うまくつながれない」 という切実な心の痛みがあるかもしれないことを、どうか忘れないでください。
それはあなたのせいじゃない
「こんな自分はおかしい」「弱いんだ」──
そうやって自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
でも、それは心がどうにかして生き延びようとした結果。
あなたなりに、バランスを取ろうとがんばってきた証なのです。
感情を感じないようにすること。
食べないことで、心のバランスを保ってきたこと。
それは、あなたなりの精いっぱいのやり方だったのです。
「ここまで生き延びてきた自分」を責めるのではなく、
「よくやってきたね」と、そっと声をかけてあげること。
そこから、少しずつ回復は始まっていきます。
回復の入り口:安全なつながりを取り戻す
ただ「食べられるようになる」だけでは足りない
摂食障害の回復というと、「きちんと食べられるようになること」がゴールのように思われがちです。
けれど、本当の回復には、その背景にある心の痛みに向き合うことが欠かせません。
たとえば、誰にもわかってもらえなかった気持ちや、自分の気持ちを否定され続けてきた日々、頑張っても認めてもらえなかった孤独感……
そうした思いを抱えたままでは、「とにかく食べればいい」と言われても、心が置き去りになってしまいます。
回復とは、「もう、食べることに頼らなくても、この気持ちに向き合える」という力を、少しずつ取り戻していくプロセスです。
そしてそれは、「ひとりで抱え込まなくてもいい」と感じられる、安心できる人とのつながりの中で育まれていくのです。
「頼ってもいい」と思える経験が、心の土台になる
「わかってくれる」「ここにいていい」と思えるような安全な人との関係が、 回復を支える大切な土台になります。
たとえば、「本当は食べたい。でも怖い」と言葉にしたとき、否定されずに「怖いよね」と共感してもらえた瞬間。
その体験は、「感じてはいけないと思っていた気持ちを、安心して出してもいい」と思えるきっかけになります。
また、信頼できる友人やパートナーに、「つらいときにそばにいてくれてうれしかった」と伝えた経験が、「頼っても大丈夫」という感覚を育てていくきっかけになることもあります。
さらに、自分自身が誰かにつらい気持ちを打ち明けられ、そばにいることで相手が安心した──そんな経験をしたとき、人は「弱さを見せることも人をつなぐ力になる」と実感します。
その体験は、「人は支え合っていいんだ」「弱さを分かち合うことで関係は深まるんだ」という感覚を育て、やがて「自分もつらいときには誰かを頼っていい」と思える力へと変わっていきます。
支えることも、支えられることも、どちらも人とのつながりの中にある自然な営み。
そうした経験の積み重ねが、「食べる・食べない」でしか表現できなかった気持ちを、人との関係の中で共有できる力へと変えていきます。
「もう、ひとりでがんばらなくていい」と思えること──それが、回復の入口。
そしてその第一歩を支えるのは、「安心して頼れるつながり」という心の土台なのです。
おわりに:食べる/食べない、その奥にあるもの
摂食障害は、「食べる」「食べない」の問題に見えて、 実は心の奥にある“つながりの痛み”や“わかってほしい気持ち”が表れていることが多いのです。
「なぜそうなったのか」「どうしてそうせざるを得なかったのか?」を見つめることで、 今までとは違う視点で自分を理解できるようになります。
焦らなくて大丈夫。 あなたのペースで、自分の気持ちとつながり直していけますように。
回復された方・変化を実感された方
実際の体験談を読む
体験カウンセリング
(オンライン)