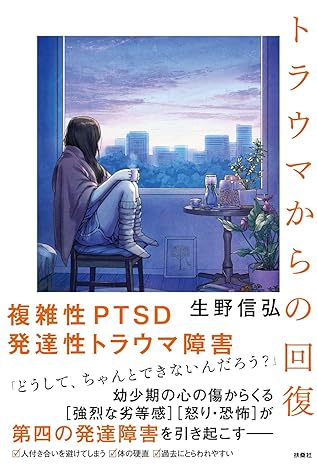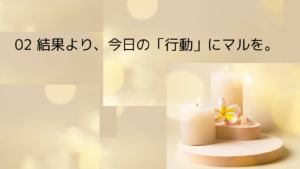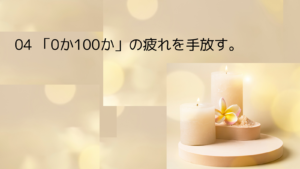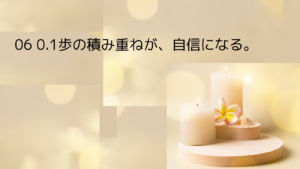トラウマによって引き起こされる反応は決してあなたの弱さではありません。それは、あなたが困難な状況を生き抜くために起こった、心身の自然な働きなのです。多くの方がトラウマから回復し、再び穏やかな日常を取り戻されています。この記事では、臨床心理学の視点から、トラウマの定義、種類、心と体への影響について丁寧に解説します。
単回性トラウマ、複雑性トラウマ、発達性トラウマの違いを理解し、自分に起きていることを「正しく知る」ことが回復の第一歩になります。焦らず、あなたのペースで、一緒に理解を深めていきましょう。
生野 信弘
1988年長崎大学医学部卒業。医学博士。
2001年に内科から精神科に転向後は、過食症の対人関係療法とともに、「複雑性PTSD」などトラウマ疾患を専門に外来診療を行ってきた。『トラウマからの回復』の著者でもある。
トラウマとは何か──臨床心理学の定義と分類
心的外傷(Trauma)とは:DSM-5における定義
トラウマとは、命の危険を感じるような非常に強烈な体験をしたことで、心に深い傷が残ってしまうことです。それは、自分自身が実際に経験した出来事に限らず、以下のようなケースも含まれます
- 他人がそのような危険な状況に巻き込まれる瞬間を目撃した場合
- とても親しい人が深刻な事故や事件に巻き込まれたという話を聞いた場合
心的外傷(Trauma)は、DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)という精神医学の診断基準で、以下のように定義されています。
- 心的外傷的出来事を直接体験する
- 他人に起こった出来事を直に目撃する
- 近親者または親しい友人に起こった心的外傷的出来事を耳にする
- 心的外傷的出来事の強い不快感を抱く細部に、繰り返しまたは極端に暴露される体験をする
引用:DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引き
具体的に説明すると以下のようになります。
- 自身が死ぬかもしれない、大けがをするかもしれない、または強い恐怖を感じるような出来事を直接経験した場合を指します。例えば、交通事故で九死に一生を得たり、犯罪に巻き込まれて暴力を受けたり、性的な被害に遭ったりすることが当てはまります。
- 他の方が死んでしまったり、重傷を負ったり、性的な暴力を受けたりする瞬間を、直接見てしまった場合を指します。
- 家族やとても親しい友人が、命に関わるような事故や事件に遭ったことを聞いた場合を指します。単に事故や事件に遭ったというだけでなく、実際に亡くなってしまったり、生死をさまようような重傷を負ったりした場合に限られます。
- 目を背けたくなるような酷い出来事の詳細に、仕事を通して何度も、または極端な形で触れることを指します。例えば、虐待やネグレクト、家庭内暴力の被害者の遺体を何度も見たり、児童虐待の繰り返しの詳細な話を聞いたりするなどです。電子媒体、テレビ、映像、または写真を見たという場合には適用されず、仕事に関するものに限られます。
このように、トラウマのきっかけとなる出来事は、自分に直接おこったものに限らず、様々な状況が考えられます。共通しているのは、その出来事が非常に衝撃的で、心に強い恐怖や苦痛を与え、その後の生活にまで影響を及ぼしてしまう可能性があるということです。
トラウマ体験の種類
心的外傷(トラウマ)は、個人の安全や尊厳が脅かされるような深刻な体験によって引き起こされます。その体験は、直接的なものだけでなく、間接的に影響を受ける場合もあります。また、DSM-5に定義されていない体験であっても、心に強い恐怖や苦痛を与え、その後の生活に影響を及ぼす場合もあります。
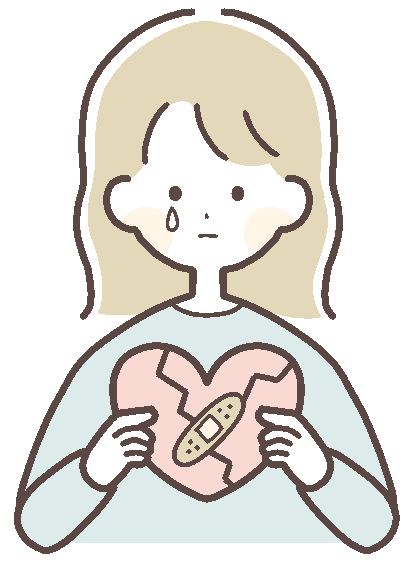
直接的な体験(DSM-5の定義による)
実際に自分が危険や苦痛にさらされた体験です。
- 身体的虐待: 殴る、蹴る、火傷を負わせるなど、身体的な苦痛を与える行為
- 性的虐待: 意図しない性的な接触、性的行為の強要、性的搾取など
- 交通事故: 自身が当事者となった、または目撃した重大な交通事故
- 自然災害: 地震、津波、台風、火災などによる生命の危機
- 犯罪被害: 暴行、強盗、誘拐など、犯罪に巻き込まれること
- 重大な病気や怪我: 生命に関わるような病気や事故による重傷
- 医療処置: 手術や侵襲的な検査など、身体的・精神的な苦痛を伴う医療行為
間接的な体験(DSM-5の定義による)
自分が直接被害を受けたわけではないが、心に大きな影響を与える体験です。
- 他者のトラウマ体験の目撃: 家族や親しい人が虐待や暴力、事故などに遭うのを目撃すること
DSM-5に定義されていないが、その後の生活に影響を及ぼす可能性のある体験
- 心理的虐待: 暴言、侮辱、無視、脅迫、孤立させるなど、精神的な苦痛を与える行為
- ネグレクト: 衣食住や医療、教育などの必要な世話を怠ること
- 家庭内暴力: 配偶者や家族間の暴力
- いじめ: 学校や職場などでの継続的な嫌がらせや暴力
- 災害や事故の報道: 悲惨な事件や事故の報道に繰り返し触れること
- 虐待やネグレクトの環境で育つ: 直接的な被害を受けなくても、不安定で危険な環境で育つこと
PTSDなどのトラウマ関連疾患との関係
「トラウマ」とは、心に深く残るつらい体験の記憶そのものを指します。しかし、その体験が心や体に長期的な影響を与え、日常生活に支障をきたすようになると、「トラウマ関連疾患」と診断されることがあります。
つらい出来事の後に、強いストレスや不安、落ち込みなどが生じるのは、誰にでも起こりうる自然な反応です。多くの場合、時間の経過とともに症状は軽減していきますが、以下のような状態が続く場合は注意が必要です。
- トラウマとなった出来事の記憶が何度もよみがえる(フラッシュバック)
- 悪夢を見る
- 強い不安や恐怖が続く
- 日常生活に支障が出るほどの回避行動や過敏な反応がある
さらに、トラウマの種類や経過によって、以下のような疾患に分類されることがあります:
- PTSD(心的外傷後ストレス障害):一度限りの事故や災害、暴力などの単回性トラウマによって生じる
- 複雑性PTSD:長期間にわたり繰り返される虐待や暴力など、慢性的なトラウマ体験によって発症する
- 発達性トラウマ障害:幼少期における継続的なネグレクトや不適切な養育環境が影響し、心の発達に深刻な影響を及ぼす
単回性トラウマ vs 複雑性トラウマ vs 発達性トラウマ
トラウマは、その発生の仕方や体験の背景によって、いくつかのタイプに分類されます。ここでは主に以下の3種類に分けて、その違いを解説します。
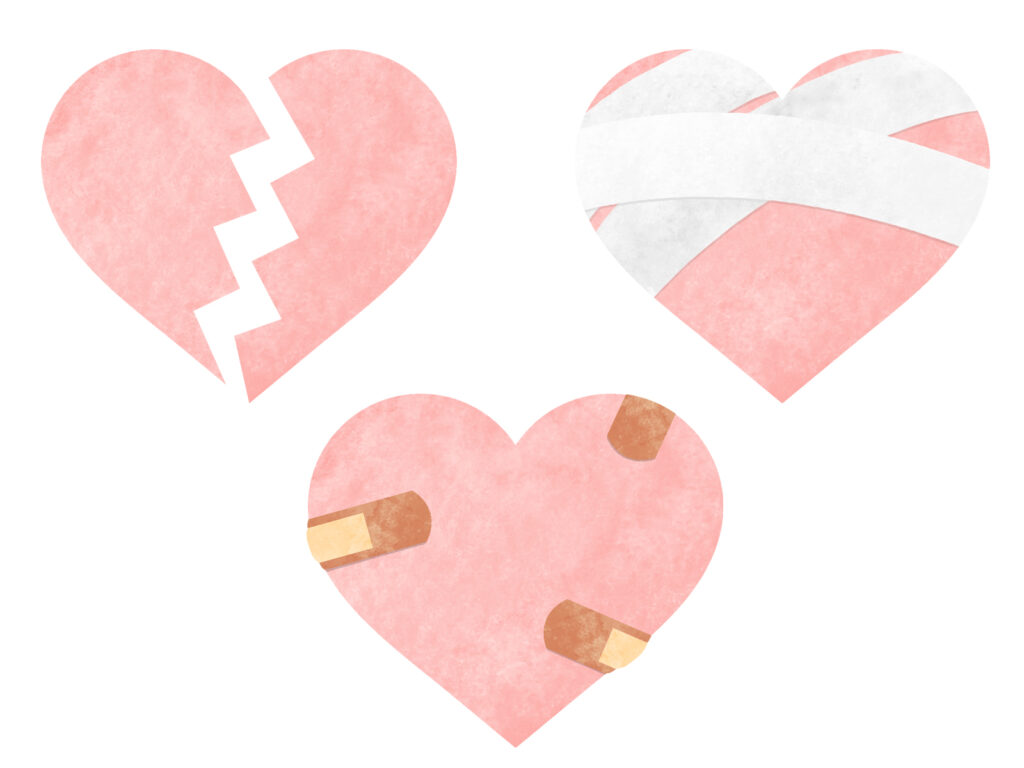
単回性トラウマとは
一度きりの強烈で衝撃的な出来事によって引き起こされるトラウマです。たとえば、交通事故、自然災害、暴行被害など、予期せぬ出来事が心に大きな傷を残します。
複雑性トラウマとは
虐待やネグレクト、家庭内暴力、いじめなど、長期的かつ反復的なトラウマ体験が心に深く影響を及ぼすものです。トラウマが慢性的に蓄積されることで、感情調整や対人関係に困難をきたす傾向があります。
発達性トラウマとは
幼少期に安全であるはずの家庭環境が不安定だったり、ネグレクト(無視)や心理的な虐待など(逆境的小児期体験)があると、子どもの心に深い傷(発達性トラウマ)を残します。子どもは庇護される存在であることや大人にとっては小さいことでも強い恐怖を感じることもあり、出来事の大きさだけでなく、その時に養育者に適切にケアされたかどうかがトラウマとして心に残るかに影響するのです。
| 特徴 | 単回性トラウマ | 複雑性トラウマ | 発達性トラウマ |
| 原因となる体験 | 一度の強烈な出来事 | 長期間にわたる反復的なトラウマ体験 | 幼少期から青年期にかけての持続的な不適切な養育環境(逆境的小児期体験) |
| 主な時期 | 人生のどの時点でも起こりうる | 主に成人期以降に影響が顕在化しやすい | 幼少期から青年期 |
| 主な影響 | PTSDの症状(再体験、回避、過覚醒) | PTSDの症状 + 自己組織化の障害(感情調整困難、否定的な自己概念、対人関係困難) | 愛着の問題、自己同一性の拡散、解離症状、身体症状、リスク行動など、広範囲にわたる発達への影響 |
| 関連する概念 | PTSD | 複雑性PTSD | 愛着障害、発達障害(誤診の可能性もある)、境界性パーソナリティ障害など |
トラウマによる心理的・身体的な影響
フラッシュバック・回避行動・過覚醒などの主な症状
トラウマ体験のあと、多くの人が共通して経験する代表的な症状には、以下の3つがあります。
フラッシュバック(再体験)
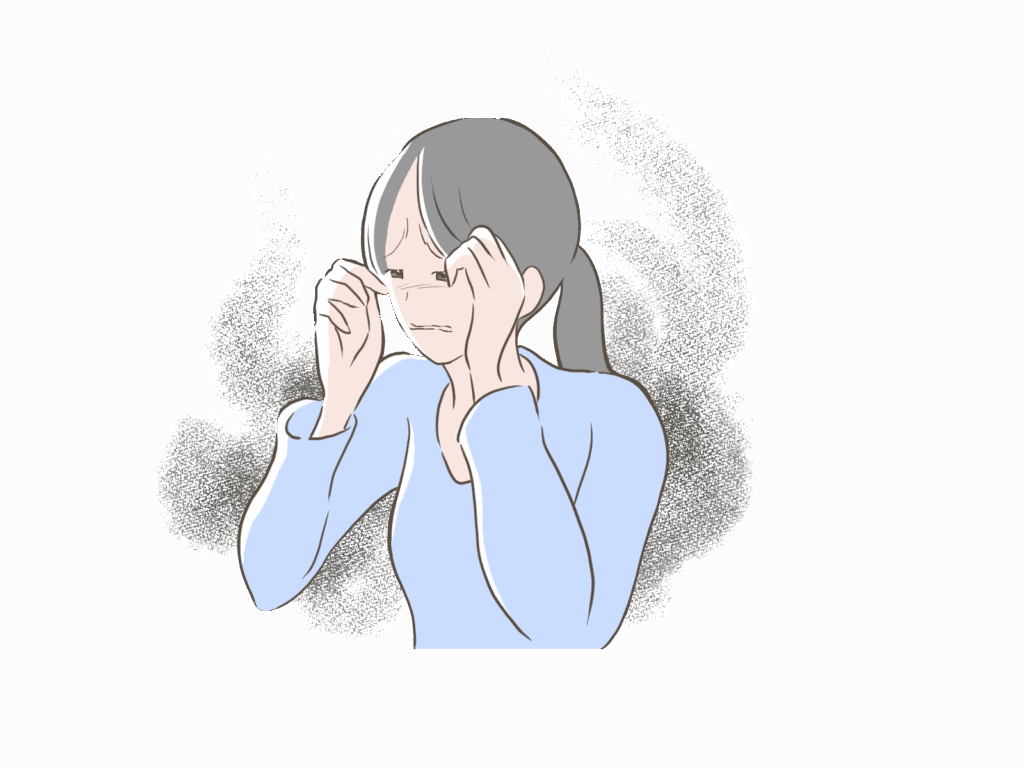
トラウマ体験が、まるで今まさに起きているかのように蘇る現象です。五感を伴った鮮明な記憶が突然よみがえり、激しい恐怖や不安を引き起こします。日常生活に重大な支障をきたすこともあります。
回避行動
つらい記憶や感情を思い出さないよう、特定の場所、人、会話、活動などを避ける行動です。一時的には心の負担を軽減しますが、徐々に社会的孤立や生活範囲の制限を招く可能性があります。
過覚醒(過剰な警戒状態)
常に神経が張り詰め、ささいな刺激にも過敏に反応する状態です。眠りが浅い、集中力が続かない、突然イライラするなどの症状が表れ、安全を感じられないままの生活が続きます。
複雑性トラウマに特有の症状
複雑性トラウマでは、上記の症状に加え、以下のような「自己」と「対人関係」への影響が強く見られます。
- 感情調節の困難:怒りや悲しみが抑えきれなくなったり、逆に感情が麻痺して無感覚になる
- 否定的な自己概念:「自分には価値がない」「すべて自分のせいだ」といった深い自己否定や恥の感情
- 対人関係の困難:親密な関係を築くことが難しく、人と距離を取りすぎたり、依存しすぎたりする傾向
発達性トラウマに特有の症状
発達性トラウマは、幼少期の持続的な不適切な養育環境によるもので、以下のような広範な影響をもたらすことがあります。
- 愛着の問題:他者への不信や過度な依存によって、安定した関係を築けない
- 自己同一性の不安定さ:「自分が誰なのか」「何を感じているのか」がわからない
- 解離症状:現実感の喪失、自分が自分でないような感覚、時間の記憶が飛ぶ
- 身体症状:原因不明の慢性的な痛みや不調
- リスク行動:自傷行為、薬物やアルコールの乱用、性的逸脱行動など
複雑性トラウマと発達性トラウマの概念は密接に関連しており、重複する側面も多くあります。幼少期の複雑なトラウマ体験は、発達性トラウマの影響を深く、広範囲に及ぼす可能性があります。
自律神経系(交感神経優位)とトラウマ反応の関係
私たちの生命維持を司る自律神経系は、活動の交感神経と休息の副交感神経からなります。しかし、トラウマ理解にはポリヴェーガル理論に基づき、交感神経、腹側迷走神経、背側迷走神経の3つで捉えることが有効です。
安全な状況では、腹側迷走神経が優位に働き、表情、声、聴覚を通じて他者との繋がりや安心感を生み出します。これにより、私たちは穏やかで協調的な関係を築けます。
一方、生命の危機に直面すると背側迷走神経が活性化し、心拍数や呼吸数を低下させ、不動化や解離を引き起こします。これは、動けない状況でエネルギーを節約し、苦痛を軽減するための適応反応です。
トラウマ体験はこの防御反応を強く引き起こし、危険が去っても自律神経系が安全な状態に戻りにくくなることがあり、交感神経優位の状態が続くことがあります。これが常に警戒し過剰に反応する過覚醒につながります。
さらに、強いトラウマや長期にわたるトラウマは背側迷走神経を過剰に活性化させ、不動化状態が続くこともあり、無気力、抑うつ、社会的な引きこもりといった症状が現れます。
フラッシュバック時には、交感神経が急激に活性化し、まるで再び危険が訪れたかのような強い恐怖と身体反応(動悸、震え、過呼吸、発汗、めまいなど)を引き起こします。
アタッチメント(愛着)と未処理の感情

幼少期の養育者との関係で育まれるアタッチメントは、その後の人間関係や心の安定にとても大きな影響を与えます。もし、 養育者のアタッチメントが不安定だったり、養育者自身が過去のトラウマを抱えていたりすると、子どもは安心感や安全感を得ることが難しくなり、心の中に未処理の感情が溜まってしまいがちです。
そのような子どもはトラウマを受けやすい状態であり、安心できない環境の中でつらい経験を繰り返し受けると、自分自身は安全な存在ではないと感じたり、周りの人を信頼できなくなったりします。その結果、困った時に養育者に頼ろうとする自然な行動の発達がうまくいかなくなってしまうのです。
このように、アタッチメントの問題とトラウマは、お互いに影響し合って悪循環を生み出します。その結果、意欲や我慢する力、自分や他人を思いやる心、感情をコントロールする力など、社会で生きていく上で大切な力の発達にも影響が出てきてしまうこともあるのです。大人になってからのフラッシュバックや、人を避けたり依存したりする行動、感情のコントロールが難しいといった問題の背景には、こうした未処理の感情と、それに伴う不安定なアタッチメントが深く関わっていることがあります。
トラウマがその後の人生に及ぼす影響について:自己否定・人間関係・依存傾向など
過去のトラウマ体験は、その後の人生に深く、そして多岐にわたる影響を及ぼすことがあります。また、愛着の問題とトラウマが複雑に絡み合っている状態では、自己に対する認識、他者との関係性、そして心の安定にまで及ぶことがあります。
自己否定
トラウマ体験は自己価値を深く傷つけ、否定的な感情を根強くすることがあります。「自分のせいだ」と捉えてしまうことで、本来責任のない出来事にも罪悪感を抱き、自責の念に苦しむことがあります。また、どうにもできない状況に置かれた経験から無力感や絶望感を覚え、「何をやっても無駄だ」と感じてしまうことも。最悪の場合、自分の存在そのものを嫌悪し、自己を受け入れられなくなるほど自己否定が強まることもあります。

人間関係の問題
トラウマ体験は、「また裏切られるのではないか」「傷つけられるのではないか」などの他者への不信感を生み、親密な関係を避ける、あるいは疑心暗鬼になる原因となります。深い関係を持つことへの不安から表面的な付き合いに終始したり、逆に過度な依存や共依存的な関係を築こうとしたりすることも。過去のトラウマと似た状況に過敏に反応するなど、対人関係において様々な困難を引き起こします。
依存傾向
トラウマによる心の傷つきを和らげる代償として、アルコール、薬物、ギャンブル、買い物、セックス、インターネットなど、様々なものへの依存が生じることがあります。これらは一時的な苦痛からの逃避手段となりえますが、根本的な解決にはならず、長期的な視点で見ると心身の健康や社会生活に深刻な悪影響を及ぼすことがあります。
その他の心理・身体的影響
トラウマ体験は、感情や思考だけでなく、身体や認知機能、世界の捉え方にも深く影響を及ぼします。以下に、代表的な影響をいくつか挙げます。
- 感情の調節困難
- 些細なことで怒りや不安が爆発する爆発すなど感情の波が激しくなったり、逆に特定の感情を感じにくくなったりすることがあります。
- 解離症状
- 現実感が薄れたり、自分の体や感情から切り離されたような感覚を覚えたりすることがあります。辛い記憶を思い出せない、時間や場所の感覚が曖昧になるなども解離の一種です。
- 身体症状
- 頭痛、腹痛、慢性的な疲労感、睡眠障害など、心の問題が身体的な症状として現れることがあります。
- 集中力・記憶力の低下
- トラウマ体験による精神的な負担が、集中力や記憶力に影響を与えることがあります。
- 人生観の変化
- トラウマ体験を通して、世界や人間に対する見方が大きく変わることがあります。例えば、「世界は危険な場所だ」と感じたり、「誰も信じられない」と感じたりするなどです。
まとめ
トラウマによって引き起こされる反応は、心の弱さによって生じるものではなく、誰にでも起こりうる「生き延びるための自然な反応」です。
本記事では、DSM-5に基づく定義から、トラウマの種類(単回性・複雑性・発達性)、そして心と身体に及ぼす具体的な影響までを、臨床心理学の視点で解説しました。
トラウマは、感情のコントロールや人間関係、自己肯定感、身体的な症状など、人生のあらゆる側面に深く関わります。特に複雑性や発達性トラウマは、長期的かつ広範囲に影響を及ぼすことが多く、気づかぬうちに生きづらさを抱えていることもあります。
しかし、トラウマは理解され、適切に向き合うことで、少しずつ癒しと回復の道を歩むことができます。
こちらの記事では、「トラウマからの回復プロセス」について、心理的な安全感の回復や自己理解の深め方、専門的支援の選び方などを具体的にご紹介していきます。

つらさの中にいるあなたにとって、この情報が少しでも「安心」と「希望」につながるきっかけとなれば幸いです。
回復された方・変化を実感された方
実際の体験談を読む
体験カウンセリング
(オンライン)