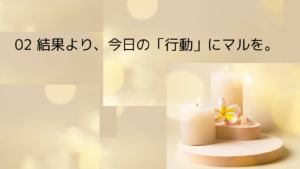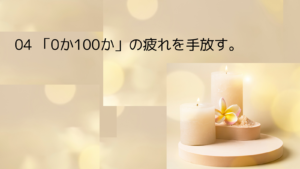摂食障害から回復するためには以下のようなアプローチを、必要なタイミングで行います。(注:順番に行うわけではありません)
・生活リズムや食事のとり方に向き合う
・自分の考えと向き合う
・自分の感情と向き合う
・「摂食障害行動」から「自分のニーズを満たすための行動」へのシフト
・過食衝動と向き合う
・他者との関係に向き合う
この記事を読まれている方の中には、摂食障害から回復したいと思っている方やそのご家族が多いと思います。そのような当事者の方々にとって、食事のとり方に向き合うということはとてもハードルが高く感じられるかもしれません。
これまでいろいろ試行錯誤されてきた方も多いと思います。
うまく食べられない日があったり、そのために夜更かししてしまったり、つらくて布団から出たくない日があったりすると、そのたびに自分を責めて悪循環に陥ったことも多いのではないでしょうか。
でも、回復の道のりで目指すことは、すべての食事をすぐに完璧に取れるようにするということでも、毎日早寝早起きをするということもありません。
例えば、一方的にちゃんと食べなさいとか、早寝早起きしなさいと言われると反発したくなりますよね。
かといって、理屈で説得されてもやっぱり続かない。
どうせ私にはできないし…としていても、できない自分を責めるところに戻ってきてしまう。
目指すのは食事や生活リズムと向き合うこころの姿勢を作ることです。
摂食障害から回復した方たちは、食事や睡眠を完璧に規則正しくとることができるようになった人たちではなく、時にはうまくいかなくてもそんな自分自身に向き合うこころの姿勢を少しずつ育てていった人たちなのです。
このこころの姿勢を育てるということは、自分の中に『自分自身への温かいまなざし』と『自分が必要とする方向に進めるように導く明晰さ』を持った“頼りになる部分”を育てるということです。
そしてその“頼りになる部分”は、回復までの道のりを進む間に磨かれ、回復後もずっとあなたを支え続けます。
ホルモンと神経伝達物質
自分の中に『自分自身への温かいまなざし』と『自分が必要とする方向に進めるように導く明晰さ』を持った“頼りになる部分”を育てるためには、ある程度の知識や情報が必要です。
ここでは、食事と睡眠がどんなふうに影響しあっているかを理解していきましょう。
さて、いきなりですが食事と睡眠にはいつくかのホルモンや神経伝達物質が関与しています。
今回はそのなかでも以下の三つについて取り上げます。
グレリン:胃から分泌されるホルモンで、食欲を増加させる作用があります。空腹時や睡眠不足のときに分泌が亢進します。
レプチン:脂肪細胞から分泌されるホルモンで、食欲を抑制させる作用があります。満腹になると分泌され、催眠作用もあります。
オレキシン:脳の視床下部で分泌される神経伝達物質です。覚醒と睡眠を調節します。オレキシンが増えると覚醒状態になります。また、グレリンの増加とレプチンの減少でオレキシンは増加します。
睡眠不足の状態が続くとそれだけでもグレリンが分泌されやすくなってしまい、常に何か食べたい、あるいはいつも食べ物のことを考えているという状態になりやすくなるのです。
そこに空腹状態が加わるとその傾向はさらに強まると考えられます。さらに、グレリンの分泌が増加し、レプチンは分泌されにくいため、オレキシンが増加してしまい、ますます覚醒状態を助長してしまうのです。
そして、慢性的な不眠が起こりやすくなり、常にグレリンの分泌が亢進するという悪循環が起こり、食べたい気持ちに支配されやすし、うまく眠れないというつらい状態が続いてしまいます。
このような状態だと回復への道のりを歩み続けるのはとてもつらくなってしまいます。なぜなら、脳も体もまずは身体的な安全を守ろうと必死で、それどころではなくなってしまうからです。
うまくいかなくても
けれど、どんなに頑張って取り組んでいてもうまくいかないときがあります。どんな人でもいつもうまくいくわけではないですから。
とにかくちゃんとやらなきゃという姿勢で取り組むと、うまく眠れていないのに、今日も早く起きろ!とお尻を叩くかもしれません。三食ちゃんと食べなきゃと食べられる食べ物を買い占めたり、手に入らないと絶望するかもしれません。
理屈や知識に従ってばかりだと、うまく食べられなかった時のつじつま合わせに、次の食事でどう調整しようかと逆に食べ過ぎてしまうかもしれません。
完璧主義思考とかべき思考が隠れていそうですね。こうして回復したいという期待からの行動が、義務に変わっていってしまいます。
そして、もうどうせ無理…となってしまう。
うまくいかなかったときは、残念な気持ちや悔しい気持ちがあることに気づいてあげましょう。
回復するために頑張っているのになかなかうまくいかなくて、すごくもどかしい気持ちにただ気づいて、認めてあげてください。
その気づきが“頼りになる部分”に育っていきます。
そしていつかその残念な気持ち、悔しい気持ちにただ身をゆだねることができる時が来ます。今はまだ難しくても、まずは気づくことを重ねていくことから始めましょう。
症状をコントロールしようとすることの弊害
ところで、過食や過食嘔吐をやめようといろいろ工夫したことがある方は少なくないと思います。カウンセリング中によく耳にするのは、過食を引き起こしそうな食べ物を避けたり、予定を詰め込んで過食する暇をなくそうとしたり、誰かと一緒に食事をするなどです。
どれも一時的には効果があるかもしれませんが、反動であとから過食したくなってしまいます。これらのやり方は過食や過食嘔吐を避けようとして行っている行動ですが、逆にずっと過食や過食嘔吐のことを意識している状態なのです。過食しないで済んでいても常にそのことにとらわれているのです。
反動で起こる過食はより強い衝動になることもありますし、何より自分なりの工夫や努力がうまくいかなかった悔しさや無力感でますますつらくなってしまいます。
するかしないかの白黒思考にもつながりますし、回避的な行動や強迫的な行動を引き起こしやすくもなります。
回復への長期的視点を意識した土台作り
長期的な視点を持つことは様々な場面で重要なことですが、摂食障害からの回復でもそれは同じです。長期的な視点を持って取り組むことは、上記のような反動を起こさないためだけでなく、過食や過食嘔吐の症状がある方の多くが持っている衝動性をコントロールできるようになるためにも重要です。
摂食障害から回復する道のりでは、最初に挙げたように、自分と向き合い、他者との関係にも向き合うことを丁寧にじっくりと行っていきます。その道のりを進んでいくためには、食事や睡眠などの身体的な安定という土台と自分に向き合う姿勢という土台を作ることが、長期的な視点で重要になるのです。
これらの土台作りは、リューココリーネで一緒に取り組むことができるものもあれば、他の相談機関と並行して行う必要があるものもあります。あなたにとってどうしていくのがいいか一緒に考えていきましょう。
それから、カウンセリング中に食事を制限したくなったり、生活リズムが崩れてしまうこともあると思います。私がこのように”食事と生活リズムは土台だ”などと書いていると、そういったことを言い出しにくくなってしまうかもしれません。
ですが、そうなってしまったのには必ず事情があるはずなのです。食事を抜きたくなった事情、生活リズムが崩れた事情などを一緒に振り返っていきますから、心配しないで教えてくださいね。
みなさんが回復への道のりを進むための土台作りに、今回の記事が役に立つことを願っています。
回復された方・変化を実感された方
実際の体験談を読む
体験カウンセリング
(オンライン)