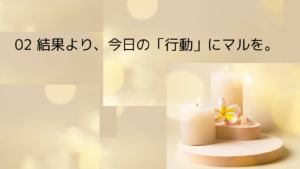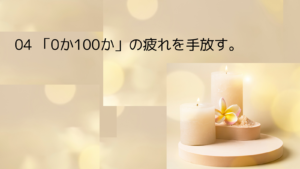「断れない」「相手に合わせすぎて疲れてしまう」「本当は嫌なのに笑って合わせてしまう」——。
こうした経験、あなたにもありませんか?
摂食障害やトラウマを抱える方の多くが共通して感じるのが、自分と相手の間に心の境界線(バウンダリー)を引くことのむずかしさです。
心の境界線は、実は私たちの生き方や人間関係、そして心身の健康に深く関わっています。
この記事では、心の境界線を引くことがなぜ難しく感じられるのか、摂食障害やトラウマとどのように関係しているのか、そして小さな一歩をどう踏み出せるのかを、やさしく解説します。

上畠 真紀
公認心理師、精神保健福祉士
経験
18年以上のカウンセリング経験(精神科・心療内科)
専門分野
摂食障害、気分障害、トラウマ、対人関係
境界線(バウンダリー)とは?
境界線は、自分と相手を区切る「見えない線」のことです。
- どこまでが自分の気持ちで、どこからが相手の気持ちなのか
- 何を引き受けられて、何は難しいのか
- 自分の時間や体を、どの範囲まで相手に使えるのか
この線を引けると、人との関係がぐっと楽になります。
逆に、この線があいまいだと「どこまでが自分で、どこまでが相手なのか」がわからなくなり、疲れやすくなってしまいます。
よく誤解されるのは、「境界線を持つこと=わがまま」だという考え方。
けれど本当は逆で、境界線を持つことは自分も相手も大切にするために必要なものなのです。
境界線が崩れるとどうなる?
境界線がうまく引けないと、心や体にさまざまな影響があらわれます。
- 相手の気持ちを優先しすぎて、自分の気持ちがわからなくなる
- 「嫌だ」と感じても飲み込んでしまい、断れずに無理を重ねてしまう
- 相手の感情に巻き込まれ、自分までしんどくなる
- 常に気を張っていて、疲れやすくなる
- 心が休まらず、眠れなかったり、体調を崩したりする
このような状態が続くと、「自分は何を感じているのか」「どうしたいのか」がわからなくなり、自分の内側とつながる感覚が薄れていきます。
そして、その“しんどさ”を何とかしようと、無意識に別の方法でバランスを取ろうとすることがあります。
摂食障害の症状は、その一つの現れです。
たとえば、誰かに気をつかいすぎて疲れたあと、無意識に食べすぎてしまうことがあります。
それは、他人に入り込まれたような感覚から、自分の心を守ろうとする自然な反応かもしれません。
また、食べることや体重の管理を通して「安心を感じようとする」「自分の存在価値を保つ」といった行動が出ることもあります。
このように、摂食障害の症状は、心の境界線を守ろうとする“代わりの方法”としてあらわれることがあるのです。
「わかっていてもできない」苦しさ
ここで多くの方が悩むのが、「頭ではわかっているのに、うまく実行できない」ことです。
- 「嫌だと言ったら相手が離れてしまうのでは?」
- 「断ったら嫌われるのでは?」
- 「自分が我慢すれば丸く収まる」
こう思ってしまい、結局言えないことが多いのです。
心理学では「認知と行動のギャップ」と呼ばれる現象があります。
これは、頭では「こうしたほうがいい」「自分の気持ちを大切にしたほうがいい」と理解していても、心や体がついていかず、実際の行動にはなかなか移せない状態のことです。
特にトラウマ体験や愛着の傷つきがあると、「NOを言う=危険」と心が無意識に感じてしまい、行動に移せないことがあるのです。
なぜ境界線はむずかしいの?
「どうして私は、境界線を引くことが苦手なんだろう?」
そう自分を責めてしまう方も多いですが、そこには必ず理由があります。
1. 幼いころの心理的環境
子どものころ、親の顔色をうかがって過ごす必要があった人は、自然と自分の気持ちより相手を優先するクセを身につけます。
- 「断ったら愛されない」
- 「嫌だと言ったら怒られる」
こうした経験は、無意識に「自分の線を引くことは危険」と学ぶきっかけになります。
心理的に「相手に合わせることが安全だ」と条件づけられて、頭ではわかっていても、心や体は反応してしまうのです。
2. 幼いころの環境要因
同じ幼少期でも、環境の具体的な条件も影響します。
- 干渉的な家庭では、自分のスペースや意見が尊重されず、境界線を育てる機会が少なかった
- 逆に放置されて「自分で全部なんとかしなきゃ」と感じる必要があった
こうした物理的・状況的な経験も、境界線を持つ感覚の育ちを妨げます。
3. トラウマ体験
怒鳴られる、見捨てられるなど、拒否や反抗が危険につながる経験があると、「NO」を出すこと自体が無意識に怖くなります。
この恐怖は、成長しても心の奥に残り、境界線を引くことを難しくします。
4. 自己価値の低さ(1〜3の結果として)
上記1~3のような心理的・環境的条件やトラウマ体験の影響で、無意識のうちに次のように感じることがあります。
• 「自分の気持ちは大事にされない」
• 「自分の気持ちを大切にする価値がない」
• 「断ったり、自分の線を引くことは許されない」
こうした感覚は、境界線を引くことが難しい原因そのものではありません。
むしろ、幼少期の環境や過去の体験によって生まれた結果として感じているものです。
5.過去の体験によるスキルと感覚の影響
つまり、境界線が引けないのはあなたの弱さではなく、過去の体験によって身につけたスキル(対処方法)と、自己価値の低さという感覚の影響です。
• 「相手に合わせて我慢する」ことは、危険を避けるために身につけたスキル(対処方法)です。
• 「NOを言うと危険」と感じる心の感覚は、体験から学んだ自動的な反応です。
これらのスキルと感覚は、かつてあなたを守る知恵として働きました。
けれど今では、境界線を引くことを難しくしてしまっています。
つまり、頭では理解していても、体や心が反応してしまい、思うように行動できない――これが、多くの人が感じる苦しさの正体です。
境界線と回復の関係
摂食障害やトラウマからの回復の中で大切なのは、「安心できる人間関係を取り戻すこと」です。
カウンセリングや安全な関係の中で、
- 「Noと言っても関係は壊れない」
- 「自分の気持ちを尊重しても大丈夫」
という経験を少しずつ積み直すことで、境界線は育ち直すことができます。
これは一気にできることではありません。
むしろ、時間をかけて少しずつ「自分の線」を取り戻していく過程そのものが、回復の歩みになるのです。
そして境界線を持てるようになると…
- 人間関係が「しんどい」から「安心できる」に変わっていく
- 無理して食べ物に頼らなくても、心が落ち着く時間が増えていく
- 自分の気持ちを表現することが、怖さではなく安心につながっていく
こうした変化が少しずつ訪れます。
今日からできる小さなステップ
いきなり「はっきり断る」のは難しいものです。
まずは小さな練習から始めてみましょう。
1. 自分の気持ちに気づく
誰かと話したあとに、
「本当はどう感じてた?」と自分に問いかけてみる。
→ これだけでも、境界線を意識する一歩です。
2. 返事を保留する
すぐに「はい」と言わず、
「ちょっと考えてから返事するね」と伝えてみる。
→ 相手に合わせすぎない練習になります。
3. 安全な相手に小さな「嫌」を伝える
「今日は疲れているから電話はできない」
「今は一人で過ごしたい」
→ まず心の中で認めるだけでも十分です。
それを安全な相手に言葉にしてみることで、少しずつ「NOを言う力」が育ちます。。
4. 自分の安心できる時間を大切にする
人に会う予定を入れるのと同じように、
「休む時間」「好きなことをする時間」など「自分のための時間」を先に予定に書き込んでみる。読書、散歩、眠る時間など、些細なことで構いません。
→ 自分の時間を尊重することも、立派な境界線です。
5. 小さな成功体験を積み重ねる
一度の失敗であきらめず、少しずつ行動することが大切です。
「NOを言えた」「自分の時間を守れた」という経験は、心の線を育てる栄養になります。
まとめ 〜あなたの中に境界線は育て直せる〜
境界線とは、ただ「断る力」ではなく、自分を大切にしながら、相手も尊重する心の線です。
境界線を引くのが苦手でも、それは決してあなたが弱いからではありません。
そこには必ず背景があり、あなたが一生懸命生き延びてきた証なのです。
少しずつ「小さな嫌」や「自分の時間」を守る経験を積むことで、
- 食べることにしばられない自由さ
- 人との関係での安心感
といった変化を感じられるようになります。
境界線を引けなかったのは、弱さのせいではなく、これまでそうするしかなかった背景があったからです。
だから、今から少しずつ取り戻していけば大丈夫。
あなたの中には、自分を守りながら人とつながる力が必ずあります。
その力を取り戻す一歩を踏み出すことが、心と体を守る大切な始まりです。
焦らず、少しずつでいい。あなたのペースで進めていきましょう。
回復された方・変化を実感された方
実際の体験談を読む
体験カウンセリング
(オンライン)