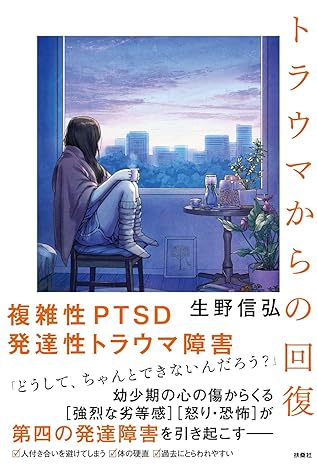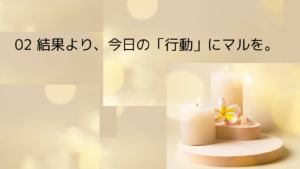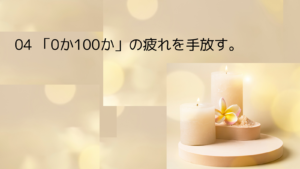人間関係に疲れを感じることは誰にでもあります。
仕事・友人・家庭など、さまざまな関係のストレスが積み重なることも…。
この記事では、原因を分析し、対処法とリラックスするための考え方を紹介します。

上畠 真紀
公認心理師、精神保健福祉士
経験
18年以上のカウンセリング経験(精神科・心療内科)
専門分野
摂食障害、気分障害、トラウマ、対人関係
人間関係に疲れる主な原因
過度な気遣い・他人の目を気にしすぎる
相手からどう思われているかが気になって、自分の意見や気持ちを表現できないことが続く背景には様々なことが考えられます。
例えば、自分に自信がない。嫌われたくないというものです。
自分自身や自分の言動に自信が持てないといつも不安な状態です。こうした傾向のある方は、嫌われることが自己評価とも関連してしまうため過剰に警戒してしまいます。そのため対人関係においても不安が強くなります。
他にも、過去の人間関係で傷ついた経験があると再び傷つくことを通常以上に恐れるようになります。
その結果、批判や否定、拒絶を恐れて相手からのネガティブな評価を避けようと自分の意見を表現できなくなったり、相手の意見に合わせるようになります。本来の自分の気分とは違う振る舞いをすることもあるかもしれません。
相手が機嫌が悪かったり落ち込んでいたりすると、その原因が自分にあるのではないかと自分を責めてしまうことも…。
こうして、自分の意見や気持ちを表現せずに抑圧することが続くと、他者との関係で安心感を感じる経験ができなくなります。そうなると、余計に自分に対してもネガティブに捉えてしまい、ますます自信が持てなくなる悪循環になってしまうのです。
価値観の違いによるストレス
私たちはそれぞれ異なる価値観を持ち、それは生き方や考え方に影響します。物事への向き合い方に対するズレは日常的なストレスにつながります。
例えば、夫婦間で価値観の違いを放置すれば生活や行動のペースがかみ合わず、わかりあえなさから孤独を感じるかもしれません。職場や友人関係でも、異なる価値観で仕事をしたり交流することは、自分と相手の価値観をすり合わせる作業が必要になり、相当な労力を伴うでしょう。
また、価値観が合わない相手と思って接することで苦手意識が強まり、固定観念や偏見から相手との間での円滑なやり取りやコミュニケーションの機会が減ってしまい、通常なら許容できることもできなくなるということもあります。
職場・家族など簡単には逃げられない関係による疲れ
職場や家族など、逃げ場のない関係性も心に大きなストレスを与えます。
ハラスメントや陰口、噂話が絶えず相談できない職場や学校では、孤立感を感じやすいでしょう。安心感を感じられない環境では集中力や思考力が低下します。余裕のなさから感情的になりやすく、さらなる人間関係の問題を引き起こしてしまうことも…。
職場にどうしても苦手な人がいるが、やりがいや家庭のことを考え、簡単に環境を変えることが難しい場合もストレスが強まります。
不登校や病気の家族がいる場合など、接し方や支え方が分からず、自分を責める気持ちで苦しくなることもあるでしょう。
こうした環境では、周囲や世間からの評価などを恐れて相談できず、一人で抱え込んでしまうことが問題を余計に悪化させてしまいます。
対人関係の疲れは“自律神経の反応”の可能性も
人間関係で感じるストレスや疲れは、心だけでなく身体の仕組みである自律神経にも関係しています。
スティーブン・ポージェス博士が提唱した「ポリヴェーガル理論」では、自律神経の働きは社会的な行動や感情の調節に影響すると示されています。
この理論では、自律神経系は以下の3つの神経回路で構成されています。
- 腹側迷走神経(社会的な関わりと安全のシステム)
- 表情、声の調子などを通じて他者とのコミュニケーションや社会的交流を円滑にする役割
- 安全な環境や信頼できる他者との関わりの中で活性化し、安心感や落ち着きをもたらし、心拍数を穏やかに保ちます。
- 交感神経系(闘争・逃走のシステム)
- 危険や脅威を感じた際に活性化する神経回路。心拍数や呼吸数を上げ、体を緊張させる。
- 衝突や批判、または予測不可能な態度を取る相手との関係は交感神経系を優位にし、慢性的な疲労感につながることがあります。
- 背側迷走神経(フリーズ(凍りつき)・シャットダウンのシステム)
- 生命の危機を感じた際に心拍数や血圧を急激に低下させ、動きを止めます。
- 社会的なつながりの欠如や、他者からの拒絶により活性化しエネルギーが枯渇して抑うつ状態につながることがあります。
人間関係における疲れは、こうした自律神経系のバランスの乱れと深く関連しています。単なる精神的な問題だけでなく、自律神経系の生理的な反応でもあるのです。
人間関係のストレスを軽減する向き合い方
自分の気持ちを大切にする
自分がどう感じているか、どうしたいと思っているかをまずは意識することが大切です。他人軸で考える習慣がついていると、初めは自分がどう感じているかうまくキャッチできないかもしれません。
最初はそれでもいいのです。どう感じているか自分自身に問いかけ続けることが自分の気持ちや自分自身を大切にすることにつながります。
自分がどうしたいのか、気づけるようになったら、必要に応じて少しずつそれを表現することを目指していけばいいのです。
「これは相手の問題」と線引きする視点を持つ 相手との境界線を意識する
相手の機嫌や気分が自分の影響によるものと考えてしまうのは、相手との間にうまく境界線が引けていないから。
あなたが発した言葉や行動が相手に影響を与えることもありますが、それは、相手の心の中で自由に起こることです。相手の育った環境や文化、その時の気分などで変わったりもします。
例えば、髪を切った友達がいて、あなたが「似合っているね」と声をかけたとします。
その友達が髪を切りすぎてがっかりしていて、さらに自分に自信がない人であれば、「嫌味かしら?」と思うかもしれません。
がっかりはしているけど、褒められたら素直に受け取れる人であれば、「案外悪くないのかな?」とちょっと自信を持つかもしれません。
このように、同じように接しても相手のこころの状態次第でどう受け取られるかはいつも変わります。
相手との間に境界線を引いたうえで、相手はそんなふうに感じるんだな、そういう考え方をするんだなと一歩引いて観察するイメージで関われるといいかもしれません。
コントロールを手放す
コントロールを手放すためには、相手の考え方や気分はコントロールできないということを認識しておくことがまず大切です。
相手の価値観を変えようとすることは相手をコントロールすることだというのはわかりやすいでしょう。
また、相手の機嫌や評価を気にして自分の考え方や態度を変えることも、相手をコントロールすることにつながります。
コントロールしようとするほどに相手や状況に心が囚われてしまい、振り回されてしまい、逆効果になることも。
コントロールしたくなる自分の事情と向き合ってみるのも効果的です。例えば、「相手と仲良くなりたい」なら、自分がされると嬉しいことを行動に移すといいかもしれません。
過去の傷つきからコントロールしたくなっているのであれば、そんな自分を認めてあげましょう。
相手の価値観を理解しようという姿勢をもつことで互いの安心感につながり、相手からの理解を得られることもあります。
完璧な人間関係はないことを理解する
育った環境や文化、価値観、その時の体調や精神状態などで人それぞれ受け取り方も感じ方も変わります。さらに同じ人であってもその時々で反応が違うこともあり、意見の違いや衝突、誤解が生じることは避けられないものです。
パレートの法則(2:8の法則)から派生した「2:6:2の法則」を紹介します。
「2:6:2の法則」は、人間関係では自分に好意的な人が2割、無関心な人が6割、好意的でない人が2割という法則です。人を入れ替えてもこの割合に戻るという実験結果もあるほどです。つまり、自分に好意的でない人がいるのは自然なことなのです。
人間関係では「いつでも誰にでも好かれる」とか、「嫌な気持ちになることを完全に避ける」ことは難しいことがわかります。
この前提を理解することで人との向き合い方に余裕を持てるかもしれません。
期待の仕方を変える
自分の抱いている期待が、本当に望んでいることなのか考えることも大切です。
そして、相手にとって実現可能か、どう伝えたらいいかを考え、その期待を変えてみましょう。
例えば、残業で帰宅が遅い夫に早く帰ってきてほしいという期待を持ったとします。この時に、今の夫にそれは可能なのか考えてみるのです。もちろん、夫に確認が必要な場合もあるでしょう。
さらに、「なぜ早く帰ってきてほしいのか」、その理由を掘り下げると「たまには夫とゆっくり過ごす時間を持ちたい」という期待が見えてくるかもしれません。
自分の本当の期待がわかると、内容も伝え方も変わるでしょう。
人間関係に疲れたときの5つの対処法
①一人の時間を確保する
出来事や自分の気持ちを振り返るためにも、自分のペースを取り戻すためにも、一人になれる時間を意識して持ちましょう。ただし、対人関係自体から距離をとりすぎると、背側迷走神経の活性化により、無気力、社会的な引きこもりといった状態となってしまう可能性もあります。適度に他の対処法も取り入れていくことが大切です。
②休息とリフレッシュ
十分な睡眠、好きな音楽を聴く、アロマを焚く、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるなど、心身がリラックスできる時間を作りましょう。趣味に没頭したり、興味のあることに挑戦したりするなど、自分の心が満たされる時間を作ることも良いでしょう。
ただし、リフレッシュのための行動でさらに疲れてしまうようであれば、無理せず休息をとることを優先させましょう。
③ストレスとなっている人間関係から距離をとる
関係性によっては、メールやSNSのやり取りの頻度を少なくしたり、会う機会を減らすなどコミュニケーションを最小限にすることもいいでしょう。
家族など生活を共にしている関係であれば、片方あるいはお互いに感情的になりやすい状態のまま一緒にいると、傷つきや疲労を重ねることになりかねません。場合によっては一時的に物理的に離れることも検討してもいいかもしれません。
④相談する
利害関係のない人に話を聞いてもらうことも効果的です。言葉にすることや誰かと共有することで、心に余裕を持つことができることも。そのときは、自分の期待を明確にして話をしましょう。ただ話を聞いてほしいだけなのに、たくさんのアドバイスをもらって、余計に疲れてしまうこともあるからです。
⑤安全な社会的つながりの強化
信頼できる友人や家族との時間を意識的に増やし、安心できる人間関係を育むことが重要です。 信頼できる他者との温かい交流は、腹側迷走神経複合体を活性化させます。これにより、心身はリラックスし、安心感や幸福感が高まります。自律神経系のバランスが整いやすくなります。
⑥カウンセリングを受ける
上記のような方法で対処しても、解決しない、整理ができない場合は、専門家(カウンセラー、セラピストなど)に相談することも有効な手段です。
また、過去の人間関係で傷ついた経験から、どうしても感情的になってしまう方もいるでしょう。心に余裕がなくなっている場合は、考え方を変えること自体にますます負担がかかってしまいます。考え方を変えることが辛い方も、専門家に相談することをお勧めします。
ただ、カウンセリングも一つの人間関係。ハードルが高いと感じられるかもしれません。まずは問い合わせなど、小さな一歩から始めてみましょう。
【監修協力】ポリヴェーガル理論に関する情報については、医療的観点からの正確性を期すため、以下の医師に監修をいただいております。
生野 信弘
1988年長崎大学医学部卒業。医学博士。
2001年に内科から精神科に転向後は、過食症の対人関係療法とともに、「複雑性PTSD」などトラウマ疾患を専門に外来診療を行ってきた。『トラウマからの回復』の著者でもある。
回復された方・変化を実感された方
実際の体験談を読む
体験カウンセリング
(オンライン)